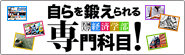学部長・学科長メッセージ
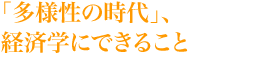
経済学科 学科長 谷村 光浩
今年はIYQ。100年前の1925年、ドイツの物理学者W.ハイゼンベルク(1901-76)が行列力学を創案し、新しい物理学である「量子力学」が生まれたことから、国連は2025年を「国際量子科学技術年」(International Year of Quantum Science and Technology: IYQ)としています。昨今、量子コンピュータ、量子暗号などに関する“理系”のニュース記事にふれる機会が増していますが、社会現象を研究の対象とする“文系”学問においても「量子社会科学」(Quantum Social Science)といった視座が提起されています。さらに今夏、「いのち輝く未来社会のデザイン」を主題に開催される大阪・関西万博では、量子世界と芸術をかけ合わせた企画もみられます。
このように現代物理学が多方面にわたり人間の暮らしや思考・表現法に大きなインパクトを与えるなか、量子力学の基礎を築いたハイゼンベルクの名は、高校教科書『古典探究』(文英堂)にも登場しています。漢文編第二部「4. 多様な考え方を学ぶ」には、荘子の「渾沌」に続き、物理学者湯川秀樹(1907-81)の著作『科学者のこころ』がコンパクトにおさめられています。
幼い頃よりお祖父さまに漢学を教わっていた著者は、「中学校に入るころには中国の古典でも、もっと面白いもの、もっと違った考え方の書物があるのではないか」とお父さまの書室を探り、「『老子』や『荘子』をひっぱりだして......『荘子』を特に面白いと思うようになった」体験から説き起こします。その後、年月を経て「素粒子のことを考えている最中に、ふと『荘子』のことを思い出した」と語り、「渾沌」の寓話を解説する段では、自身の「素粒子の研究」から「ハイゼンベルク教授」の話へと広がります。そして、「べつに昔の人の言ったことを、無理にこじつけて、今の物理学に当てはめて考える必要はない。...... 荘子が、私などが今考えていることと、ある意味で非常に似たことを考えていたということは、しかし面白いことでもあり、驚くべきことでもある」と結んでいます。
改めて、高校にて活用されている『最新政治・経済資料集2024』(第一学習社)の「経済」の始まりのページを開いてみます。いわゆる「economics」に加え、「“経済”ということばは、“経世済民”ということばを短くしたものであり、中国の故事で“世をおさめ、民を救う”の意味である」とも説き示され、「私たちの生活をよりよくしようと考えるならば、経済的なものの見方・考え方を学ぶことは有意義なこと」と記されています。
経済学科に学ばれる方々は、高校教科書のいわゆる“経済”に仕分けされている事項にかぎらず、自らが幼い頃から関心を寄せ、たとえ今は中断していても技量を磨いてきたことなどを、まずは大事に思い起こしてみてください。みなさんには、今後いかなる針路を取られようが、どの場からでも「誰も置き去りにしない」経済社会の構築にむけた広範な作業に加わっていただきたく、その基礎的な力の涵養を全力で支援します。多分野の方々との学びの場を通じて、ご自身が歴史上の先覚とも分かち合える「驚くべきこと」をいつしか見出し、それをさらに次なるステップにされることも期待しています。