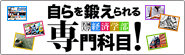経済学部ニュース
●2020年2月4日 講演会 「カブール市の雇用と衛生の課題に取り組む: アフガニスタン クリーン・グリーン・シティ プログラム」 受講報告
 |
2020年2月4日、国連ハビタット(UN-HABITAT)・福岡県国際交流センター主催の講演会に参加しました。国連ハビタット・アフガニスタン事務所の松尾敬子人間居住専門官より、首都カブール市(人口約550万)の雇用と衛生の課題解決にむけた「クリーン・グリーン・シティ プログラム」(Clean and Green Cities Programme)の背景や事業内容をうかがいました。
■「安心・安全なまちづくり」は、女性の「小さな成功」体験から
榊原えれ奈(産業社会学科2年)
カブール市が抱えるひとつの大きな課題は、「安心・安全なまちづくり」とのこと。雇用機会が限られるなかで、人々は生計を立てるために、武装勢力に加わることが少なくないそうです。特に、女性や若年層がおかれた厳しい状況を教わりました。また、市清掃局は予算不足のためにゴミ回収や道路清掃を十分に行えず、ときに詰まった排水溝は洪水さえ引き起こし、ついには行政への信頼が損なわれるという問題の構造も解説くださいました。
そうした状況のもとで、この事業では、(1)社会的に脆弱な人々が生計を立てられるような雇用機会の創出、(2)清掃を主軸に衛生環境の改善、ひいては行政への信頼向上をはかる2つのアプローチによって、社会の安寧秩序を保つという目標の達成をめざされたそうです。なお、プログラム終了後の持続的な事業運営を視野に、現地スタッフの方々も大きな責務を担い、ともに意思決定にあたる点を強調されていました。
具体的には、この事業では、経済的に困窮されている方々にカブール市の清掃員としての雇用機会が提供され、その作業に対して公務員の初任給相当の給与が支払われます。揃いのヘルメット、ベスト、手袋などを着用して安全に「仕事」にあたることを通じて、特に女性に「小さな成功」を感じてもらうこと、さらには銀行で口座を開き、そこに毎月給金が安定的に入ってくる体験や、その使い道を計画するという経験を重ねてもらうことの大切さを力説されていました。
厳しい環境を生きる現地の一人ひとりの女性がいきいきと活躍できるステージづくりを、社会に受け入れられる手立てで、なおかつ社会の問題解決もはかりながら地道に進める実践手法を、大いに学ばせていただきました。レクチャーのなかで、「アフガニスタンって本当にいいところ」と、笑顔で繰り返しお話されていましたが、その言葉には、人が人とともに強く生きていくことの大切さが込められていたように強く感じました。
■自らを信じる力、自ら歩み出す力を高めることから
筒井流水 (産業社会学科3年)
アフガニスタンの「クリーン・グリーン・シティ プログラム」の事業運営においては、特に地域コミュニティとの関わり方や、コミュニティの女性メンバーならびに現地女性スタッフの方々のエンパワーメントへの工夫を解説くださいました。
カブール市プログラム対象地区の道路や側溝の清掃、廃棄物の運搬などの作業を担う清掃員の雇用契約は、地域コミュニティを含む現地のさまざまなステークホルダーから構成されるSAB (Sanitary Advisory Board) [衛生諮問委員会] と結ばれています。プログラム終了後もこの事業が持続的に展開されるように、行政と地域コミュニティをつなぐ機関として設置されたSABでは、すでに各地区で発生するゴミの種類などの聞き取り調査なども実施されているそうです。「オレンジ色のユニフォームを着た清掃員が来ると、街がきれいになる」との認識が広がれば、行政への信頼、受益者負担への理解も高まると期待されています。社会的問題解決能力の向上が、現地の人々の絆をベースにはかられようとしています。
また、この地域においては、女性たちがワークショップに参加して意見を交わすということが困難なことから、コミュニティのなかでトレーナー役の女性メンバーが各家庭を個別に訪問し、ローカルな衛生課題をともに改善する方式が採られているとのお話もありました。このようなアプローチは、国際機関の現地女性スタッフについても同様で、松尾氏は、「女性スタッフのエンパワーメントなしに、コミュニティの女性たちのエンパワーメントはない」と強調されていました。いかなる課題の解決においても、当事者が自らを信じる力、自ら歩み出す力を高めることが重要であることを改めて感じました。
現地の女性たちが、物事を成し遂げようとする積極的な気持ちや強い責任感を抱きながらプログラムに参画される姿、そしてそうした気持ちに寄り添われる松尾氏をはじめとするアフガニスタン事務所の方々には、心より敬意を表します。防弾車両、防弾チョッキ、ヘルメットといった厳重な装備が求められる社会にあって、小さな変革や折り合いが積み重ねられるなかで、「クリーン・グリーン」「安全・安心」なまちが少しずつ広がることを願わずにはいられません。
(担当: 谷村光浩)